涼を求めて、縞枯山へ
【日程とコース】軽登山部山行〜7月27日(日)新宿7:00あずさ1⑨番線=9:07茅野9:40バス=10:25RW駅10:40=10:47山頂駅11:00-11:25雨池峠-12:20縞枯山12:30-13:20茶臼山13:30-14:15大石峠14:25-14:45麦草峠15:20バス最終=16:32茅野16:59あずさ46=19:06新宿
【メンバー】Nリーダー、Rサブリーダー、S.A、S.Y.
朝5時すぎ自宅を出た時点で、気温はすでに29度 😳 10時半ごろ北八ヶ岳ロープウェイを降り立った瞬間、空気は一変。気温は20度ほど。頬をなでる風は涼しく、全身がひんやりとした空気に包まれました。――生き返るとは、まさにこのことだと感じました。

坪庭は、八ヶ岳の噴火で生まれた溶岩台地。岩の隙間から咲く高山植物が見どころです。次回はゆっくり散策してみたい場所。
登山道を進むにつれ、森の奥はさらに冷んやりとし、静けさとともに満ちるマイナスイオンが、肌と心をやさしく潤してくれます。森がそっと寄り添ってくれているようでした。

北八ヶ岳ではシカの食害が問題になっており、ササだけが残っているのはその影響かもしれません。

縞枯山は「花の百名山」として知られていますが、心を打たれたのは花ではなく、森の気配と佇まいの美しさでした。

分岐が多くて、ちょっと迷いそうなところもある^^;

分岐….

立ち枯れた針葉樹が独特の美しさを見せてくれる

バス停に着いた直後に大雨が降り出しました。ラッキー!!
縞枯山は茶臼山と雨池峠の間に位置し、東西に約500メートルの頂上部をもつ山です。シラビソやコメツガの針葉樹林に覆われ、白く立ち枯れた木々が斜面に縞模様を描いています。「縞枯山」の名はこの風景に由来します。

※写真は北八ヶ岳ロープウェイの公式HPよりお借りしました。
縞枯れ現象とは、風雪や日射など自然の力によって、100〜300年の周期で繰り返される森林の世代交代。枯れた木々の足元には、小さな若木が芽を出し、次の命が静かに育ちはじめています。
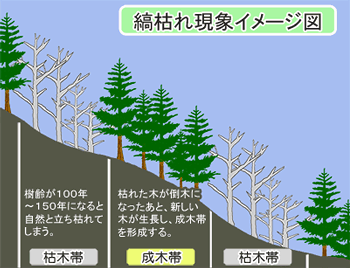

茶臼山。縞枯れ現象は「fir wave(ファー・ウェーブ)」と呼ばれる自然のサイクルで、毎年30〜60センチほど少しずつ進み、立ち枯れから新しい森が育つまでに80〜120年もかかるそうです。
やがて枯木は倒れ、土に還り、若き命の糧となる。終わりが、次の命を育てる。――その静かで力強い循環が、森にはたしかに息づいています。
世代交代とは、過去を否定することではなく、想いを未来へ託すこと。森は言葉なくして、そんな大切なことを静かに教えてくれているようでした。

ホソバミズゴケは繊維が細かく保水力も高いため、国産は少なくチリやニュージーランドからの輸入が多く、収穫や乾燥に手間がかかるぶん、普通の水苔よりずっと高価です~ by 元・盆栽愛好者

茅野駅の駅ビルには小津安二郎の特設コーナーがありました。ふと目をやると、原節子が静かにほほえんでいる。父は原節子の大ファンでした。一緒に『東京物語』を観た日の記憶は、50年たった今も色あせません。その微笑みにふれた瞬間、父がそこにいた気がしました
涼を求めての山行でしたが、学びもあり、深く心に残る時間となりました。
Nリーダー、ありがとうございました♡


